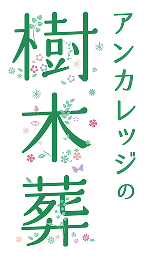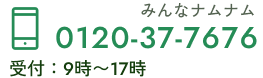「樹木葬」は、2010年代後半から急速に人気が加速している新しい "お墓の種類" です。
「自然に還る」 というイメージに好印象を持つ方も多く、この2023年以降、新規お墓購入者の過半数が樹木葬を選んでいるというアンケート結果もあります。(鎌倉新書調べ「お墓の消費者全国実態調査」)
今やお墓のスタンダードになりつつある樹木葬ですが、当然のことながら、樹木葬を選ぶことが適しているかは状況や心情によって変わってきます。
契約後に後悔しないように、まずは樹木葬がどのようなものかを知っておきましょう。
樹木葬とは?一般墓や他の埋葬方法との違い
樹木葬の特徴、一般墓との違いは?
近代の樹木葬の始まりは、1999年に岩手県の知勝院というお寺で始まったといわれています。
知勝院の樹木葬は墓所ごとに花木を1本ずつ植えるもので、里山の景観や生態系の保全を目的として始められました。
その後、樹木葬の需要が急増したのは2010年代の後半に入ってからで、従来の一般的な縦型のお墓(「代々墓」や「一般墓」と呼ばれます。ここでは以後「一般墓」と表記します。)お墓に対してまだ歴史は浅いものの、旧来の形式に捉われないお墓であるがゆえにさまざまな種類のものが生まれています。
その定義は明確ではありませんが、概ねの共通点としては、次のようなものがあります。
► 樹木や草花が墓域のメインで、大きな墓石がない
樹木葬の説明として「墓石の代わりに樹木を墓標とする」「樹木をシンボルツリーとして植える」などといわれることが多いですが、これは必ずしも正しくありません。これは樹木葬のなかでも「里山型」と呼ばれるものの特徴です。
ひと口に「樹木葬」といってもその雰囲気や仕様はさまざまで、山里そのままを利用し、個々人や区画ごとに樹木を植えるもの(里山型)や、木はないけれど解放感のある芝生のスタイル(公園型)、花の色彩に富んだもの(庭園型)などがあります。(各種類の詳細は後述)
各種類の共通点としては、墓石は無いか、あっても従来のお墓(一般墓)と比較して、かなり控えめな大きさの墓標、という点です。
今までの一般墓は、バブルの影響もあってか「大きくて立派なものを作ってこそ」という認識も広くありましたが、現代はそういった感覚を持つ方は減少してきているようです。
ご見学の方のお話を伺っていても、「仰々しい墓標は要らない」と感じる方が増えてきているように強く感じます。
► お墓の跡継ぎが不要の永代供養墓
従来のお墓は世代を超えて受け継いでいくことを前提としており、お墓を継ぐ承継者が必要でした。それに対し、樹木葬は世代間で承継しないことを前提にしている「永代供養つき」のものが主流です。基本的には、夫婦や1家族の1代限りのお墓となり、親族に代わってお寺がお墓を維持管理し、供養を行います。
承継しないというシステム上、個別の墓標を設けるタイプの樹木葬であっても、1区画ごとに人数の上限(主に1~6名前後)が決まっており、所定の期間が経過した後は墓じまいされます。
(関連記事:永代供養墓とは ―― 合同墓のこと? 今、注目されている理由は?)
近年は承継者不明のまま放置される無縁墓も社会問題になっており、今後、その予防策としても注目されています。
また、代々墓を墓じまいする際の改葬先として検討される方も多くみられます。
► 宗旨宗派(宗教)を問わず、檀家にならないでも良いことが多い
従来のお墓は、自治体の設置するお墓を除けば、お墓を持つお寺の檀家にならないと利用できませんでした。檀家になる=その宗派に入信する、という意味でもあります。
一方、樹木葬の場合は、例え寺院が管理する樹木葬であっても檀家にならなくても利用でき、宗旨宗派についても寛容であることが多くなっています。
| 特徴 | 樹木葬 | 一般墓 |
|---|---|---|
| 墓石 | なし、または控えめなサイズの墓標 | 大きな縦型墓石が一般的 |
| 承継 | 承継不要。永代供養が主流 | 世代間で承継していく |
| 宗旨宗派 | 問わない場合が多く、檀家になる必要がないことも | 原則、墓地を管理する寺院の檀家になる必要がある |
| 埋葬方法 | 他人と一緒の区画や家族ごとの区画などさまざま。土中への直接埋葬、骨壺・骨袋での埋葬など | 骨壺、または骨袋に納めて家ごとのお墓の下に埋葬 |
| 費用 | 一般墓に比べて安価な場合が多い | 墓石や管理費がかかるため高額になりがち |
| お参りのイメージ | 自然の中で故人を偲ぶ。形式は多様で自由度が高い | 墓石に向かって手を合わせる伝統的なスタイル |
樹木葬=樹木を墓標にする、とは限らない
インターネット上のフリー百科事典『Wikipedia』によると、樹木葬(じゅもくそう)は、「墓石の代わりに樹木を墓標とする墓。樹木葬墓地(じゅもくそうぼち)、樹林墓地(じゅりんぼち)とも呼ばれる。」と説明があります。
しかし、この "樹木を墓標とする" という説明は誤りです。
前述の通り、実際には、「石の墓標があるもの」「芝生に埋葬するもの(墓標代わりの木は植えない)」ものなどもあります。
樹木自体を墓標にはしていないタイプの場合であっても、墓域に木や花を植えており、 "樹木の植えられた環境の中に納骨する" という全体のイメージで以って「樹木葬」と名称しています。
「自然葬」との違い
「自然葬」は樹木葬と近似の言葉ではありますが、樹木葬だけではなく、海や山への散骨、近年提供が始まった宇宙葬なども含んだ言葉です。
代々受け継ぐような形態のお墓を持たず、ご遺骨を自然に還す形態の埋葬(葬送)全般を指して「自然葬」と呼んでいます。
樹木葬と散骨の違い
樹木葬を散骨の一種と思われる方もいますが、これも正しくはありません。
「樹木葬」は『墓地、埋葬等に関する法律』に基づいて墓地としての許可を得た「お墓」の一種です。お墓ですので、樹木葬の土中、またはカロート(墓石の下などの遺骨を納めるスペース)にご遺骨を "収蔵(埋葬)" します。
一方、「散骨」は "死者のご遺骨を粉にして海や山へ撒く葬礼" (広辞苑第7版)という行為を意味します。また、墓地への埋葬を意味する言葉でもありません。その点は海洋散骨をイメージしていただければお分かりいただけるかと思います。
注意しなくてはいけないのは、墓地(樹木葬含む)以外の場所に "散骨" をすることは必ずしも違法ではありませんが、墓地以外の場所にご遺骨を "埋葬" するのは違法(遺骨遺棄罪)であることです。
では、埋葬と散骨の違いは何か?
これも明確に違いは定められてはいませんが、一つの基準としては「遺骨が土や葉に覆われていたら埋葬」と見做される可能性があります。
樹木葬の3つの種類 ― 雰囲気は千差万別
樹木葬自体の定義が曖昧であるため、いざ樹木葬を検討しようといくつかの樹木葬墓地を見学された方の中には、その雰囲気や仕組みの多様さに驚かれる方もいます。
現在の樹木葬は、大別すると3つに分類されます。
この分類もそれぞれの定義が明確ではありませんが、おおよそのイメージを持っておくと、樹木葬を検討することになった際に戸惑わずに済むかと思います。
里山型

恐らく多くの方が「樹木葬」と聞いてまずイメージするような、山林の土中にご遺骨を埋葬するもので、より自然に近い環境の中で眠れるというのが一番の魅力です。石の墓標の代わりに花木を1本ずつ植えるものや、木は植えずに石板を置いて目印にする形態のものがあります。
冒頭に述べた通り、現代における樹木葬はこの里山型が先駆けで、1999年に岩手県の知勝院というお寺が始めたといわれています。
しかし、山の中に埋葬するため、行きにくい場所にあったり、現地に着いたあとに埋葬場所に辿りつくのにも時間がかかるような場合もあるようです。
公園型

整備された芝生にシンボルとなるツリーを数本植え、広々とした空間の心地よさを感じられる形態のものが基本です。
ご遺骨を埋葬した場所にはなんらかの目印(墓標等)が据えられることもありますが、そういったものが全くないものもあります。
都市近郊や郊外に作られることが多く、里山型に比べて交通の便は良いという利点がありますが、里山型のような "自然に還る" というイメージに強く憧れを持っている方には物足りなさを感じるかもしれません。
庭園型(ガーデニング型)

墓域全体を庭としてデザインし、植栽の美しさを楽しめる環境が整えられている樹木葬です。 庭園型樹木葬は、 "土に還りたい" という方よりも、 "美しい景観の中で眠りたい、お参りしたい" というイメージを持たれている方に合っています。
(ちなみに、この庭園型樹木葬を作った先駆けは私たちアンカレッジだと自負しております‥!)
また、公園型よりも小規模で、都市部でも作りやすいため、立地面では前の2種類に比べて多くのニーズに応えやすくなります。
例えば東京23区内に自宅がある方でも「"片道30分で行けるエリア" で "アクセス良好" な "自然豊かな環境の中で眠れる" お墓」という条件が満たせるのです。
なお、最近は「都市型樹木葬」という言葉も生まれているようですが、公園型と同義としたり、庭園型と同義としていたり、両方を指すと説明していたり‥と、解釈が曖昧です。
3つの分類と同様、「だいたいそんな感じ!」というイメージで捉えていただければと思います。
樹木葬の納骨方法 ― 心情に合わせた選択が大事
樹木葬=遺骨を土に直接埋める、という誤解
里山型であれば、恐らくほとんどの墓地が直接土に埋葬する方式だと思われますが、公園型、庭園型であれば、埋葬の仕方は墓苑ごとに異なります。
・骨壺を使用するもの
・骨袋を使用するもの
・始めは骨壺に納めた状態で納骨し、一定期間(13年、あるいは33年や50年間など)経過後は土に還るかたちで埋葬し直すもの
などがあります。
画像挿入:樹木葬の墓石の下に骨壺で納骨する様子
納骨方法の種類

納骨の仕方は概ね3つのタイプに分けられます。この分類は樹木葬にかぎらず、一般的な縦型のスタイルのお墓や納骨堂でも同様です。
► 個別埋葬
個人や家族ごとに1つの区画に納められる方式です。
ご遺骨は骨壺や骨袋などに入れられ、土には触れない状態で納められることも多くあります。
骨壺で納める場合も、一般的な陶器製の骨壺そのままで納骨できるものや、専用骨壺に移し替えるものもあります。
► 共同(集合)埋葬
家族以外のご遺骨とともに、ひとつの大きなスペースに複数人のご遺骨を埋葬します。
ご遺骨は骨壺などに入った状態で納めるので、ご遺骨自体は他人のものと混じらないようになっています。
► 合祀(合葬)
一つの空間で、家族以外の人とご遺骨が混ざるかたちで納骨されます。
場合によっては骨袋に入れた上で納骨することもありますが、時が経つにつれ布が朽ちれば、遺骨は混じっていきます。
個人で場所を占有しない分、費用が低く抑えられる傾向にあります。
その一方で、合祀されたご遺骨は、基本的には物理的に取り出すことができないというデメリットもあります。
※合祀(ごうし)、合葬(がっそう)と読みます
なお、上記3つの区別は、「土と混ざるか否か」は問いません。「土に触れるかたちで納骨される個別埋葬タイプ」「土に触れないかたちの合祀タイプ」もありえますので、混同しないようにご注意ください。
樹木葬、あるいは自然葬には、「自然に還る(≒個人としての存在感が薄まる)」というイメージが付きものです。そのため、樹木葬を希望される方には個人が区別されない合祀タイプでも抵抗がない方もいる一方で、やはりいきなり他人と一緒になることに躊躇する方もいます。また、ご遺族からすると、お参りする際に個人が区別されていないことに寂しさを感じることも多いようで、ご見学に来られるお客様からも、「墓石がないタイプのお墓も見に行ったけれど、物足りなさを感じてしまった」という声が度々聞かれます。
その点について、事前にご親族の方々のお気持ちを確認する必要があるのはもちろん、ご友人方がお墓参りを希望された場合にどちらの方が良いか、というのも考慮すると良いかもしれません。
樹木葬が注目されているのはナゼ?
ひと昔前までのお墓とは異なるスタイルである樹木葬が、近年特に注目されている要因には、次のような理由があります。
緑豊かな環境で眠り、お参りができる
従来の石が立ち並ぶ墓地を否定するわけではありませんが、「お墓で肝試し」というイメージがあるように、無機質な印象の光景に多少の怖さを感じる方も少なくありません。
それに対し、緑溢れる樹木葬はある種の生命力も感じられ、怖さはかなり軽減されます。
自分が眠る場所として、あるいは大切な方が眠る場所として、少しでも心地よさを感じられる場所を望む方が多いのです。
近年の終活の活発化に伴い、自分好みのお墓を生前の間に準備しておきたいと思う方が増えているのも、樹木葬が人気となった一因とも考えられます。
「自然に還る」というイメージの魅力
日本固有の宗教である神道では、自然や万物に神が宿ると考えています。また、ご先祖様は年数を経て神となり、海の向こう、山の向こうから子孫を見守ってくれている、という捉えかたもされます。そういった考えも影響して、故人と自然との親和性を無意識のうちに感じ取っているのかもしれません。
承継者不要の永代供養つきのお墓
樹木葬の見学に来られる方の半数以上が重要視している、といっても過言ではないポイントです。
お子様がいない方はもちろん、お子様が居たとしても、お墓を継がせることでその管理で手間をかけさせてしまうことを懸念され、敢えて継がないでも良いお墓を希望される方も多くみられます。
永代供養つきのお墓は、お墓の利用者(管理者)がいなくなったとしても、遺族の代わりにお寺が永代にわたって供養をしてくださるシステムになっており、お墓を継ぐことを前提としていません。
宗旨宗派を問わない
従来のお墓、特に寺院墓地においては、そのお寺を菩提寺(一族の遺骨を預け、供養をしてもらうお寺)とし、そのお寺の檀家となることがほぼ必須条件でした。
檀家は、親族がなくなった際には菩提寺に葬儀や法要を依頼しなくてはいけません。
しかし、永代供養墓では入檀の義務がなく、他宗派や他宗教を信仰されている方でも受け入れるケースも多くなっています。
費用が抑えられる
一般墓だと、土地の使用料に加えて墓石の購入もする必要があります。選ぶ墓石の種類や大きさによっては価格は大きく変わりますが、相場は1基あたり100万円~400万円ともいわれます、
一方、樹木葬の場合は墓石がなかったり、墓石があっても小さく、また永代供養料に墓石代も含まれていたりと、一般墓に比べて費用が抑えられる傾向にあります。相場は1霊あたり20万円程度~ともいわれます。
ただし、樹木葬であっても人数が多くなればその分高額になります。ある程度の年数は管理費が必要になることもあり、場合によっては、一般墓や他のタイプのお墓の方が割安になる可能性も。樹木葬が必ずしも "安い" わけでもないことにご注意ください。
一人分でも申し込みが可能
未婚の方、離婚された方は、ご実家のお墓には入らないこともあります。
そういった方の場合、お墓の承継がいないことも多く、一般墓を建てることが現実的ではありません。
その点、樹木葬はお一人での申し込みが可能なことが多く、また永代供養がついている点でも安心して申し込めます。
自分(たち)らしいお墓が建てられる
里山型の樹木葬をイメージされていた方には、これは意外に思われるかもしれません。
樹木葬には個別の墓石を設けるタイプもあり、イラストなどデザイン性のある彫刻ができることもあります。
ご夫婦の思い出にまつわるモチーフを彫刻したり、それぞれの趣味を象徴するイラストを施すことができます。思い出とともに眠れるのはもちろん、お参りに来られるかたも、よりその人を想い起しながら偲ぶことができるでしょう。

ペットさんと一緒のお墓に入れる
一部の樹木葬では、犬や猫などのペットさんも同じ区画、あるいは同じ敷地内に納骨できることがあります。
人間の家族と同じように(場合によってはそれ以上に...)ペットさんを大事に思う方もいらっしゃり、ペットさんと離れたくない、とペット可の樹木葬を探される方も多いです。
まとめ ―「人気」に捉われないお墓選びを
近年注目を集める新しいお墓の形、「樹木葬」について解説してきました。改めて振り返ると、樹木葬は単に「樹木を墓標にするお墓」という一言では語り尽くせない、多様な選択肢を持つ埋葬方法であることがお分かりいただけたかと思います。
樹木葬がご自身にとって最適な選択肢か否かは、価値観やライフスタイル、そして故人やご家族の想いによって変わります。
もしも、
・自然が好きで、土に還るというイメージに共感する
・お墓の継承者がいない、または負担をかけたくない
・今までのお墓のイメージにこだわらず、自由な形で故人を偲びたい
・費用を抑えたい
といった希望をお持ちであれば、樹木葬は有力な選択肢の一つとなるでしょう。
一方で、
・伝統的な家系を重視したお墓の形にこだわりたい
・将来にわたって家系のお墓を残したい
といった希望が強い場合は、他の埋葬方法も含めて慎重に検討することをおすすめします。
樹木葬だけではなく、永代供養墓(合同墓)、納骨堂、一般墓など、お墓探しのうえで選択肢は沢山あります。
お墓を探すうえで大事なのは、「人気のお墓」ということではなく、「自分にあったお墓」であること。
それぞれのメリットとデメリットをしっかりと理解し、ご自身の価値観や状況と照らして納得のいくお墓を選ぶことが大切です。