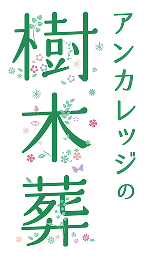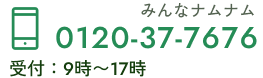お盆はいつ?新盆と旧盆の違いは?
2025年のお盆はいつ?
お盆は毎年同じ月と日で決まっていますが、2つの日程があります。
7月13日~7月16日(7月盆・新盆)、
あるいは8月13日~8月16日(8月盆・旧盆・月遅れ盆)です。
2025年も同様で、新盆は7月13日(日)~7月16日(水)、旧盆は8月13日(水)~8月16日(土)です。
7月と8月のどちらをお盆とするかは地域によって異なりますが、全国的には8月盆の地域が多いため、企業の休み(夏季休業)も8月に実施されることが多いようです。
2025年は8月11日(月)が祝日の山の日にあたるため、8月12日(火)に有給休暇を取得できれば8月9日(土)~8月17日(日)の9連休になるそうですよ...羨ましいですね。
新盆と旧盆に分かれている理由
お盆の時期が二つあるのは、使用する暦が明治時代に『太陰太陽暦(旧暦)』から『太陽暦(新暦)』に変更されたことに起因しています。
本来のお盆は7月ですが、旧暦の7月は新暦では8月頃にあたります。
その為、新暦に基づいて7月にお盆を行うようになった地域と、旧暦の7月にあたる8月に引き続きお盆を行う地域とに分かれることになりました。
なお、旧暦の7月13日~16日は、正確には新暦の8月13日~16日にはなりません。
便宜上、日にちは新暦での13日~16日で固定し、8月13日~16日で行われています。
► 新盆で行う地域
東京都、神奈川県、静岡県、北海道、石川県などの一部の地域では、新暦(現在の一般的なカレンダー)を基準にしてお盆を行います。
一説には、明治政府のお膝元であった東京は新暦に従わざるをえなかったとか...
► 旧盆で行う地域
上記以外の地域では8月の旧盆で行われ、全国的には8月盆で行うようことが多いようです。
一説には、新暦7月は繁農期にあたる為、比較的落ち着く旧暦7月に引き続きお盆を行うようになったともいわれています。
お盆は何のための行事?
仏教と日本の信仰が融合した、先祖供養と慰霊の行事
お盆は、一年に一度、ご先祖様の霊をあの世からお迎えし、感謝と供養を行う行事です。
7世紀頃に仏教行事として日本に伝わり、江戸時代には庶民の間でも広まっていたといわれています。
現在でもお盆は仏教行事と認識されていますが、実際には「家に戻ってくるご先祖様に感謝をする」という日本固有の神道的な祖霊信仰と、「ご先祖様の供養を行う」という仏教的な面が結びついたものです。
また、身内の霊だけではなく、全ての魂、あるいはあの世で餓えに苦しむ諸霊に供養を捧げる行事でもあります。
► ご先祖様や諸霊への供養としてのお盆
仏教の教えでは、他者を思いやる善行によって得られる功徳が、現世や来世での幸せにつながるとされており、この功徳を故人に分け与える「追善供養」によって、故人の成仏や来世での幸せを願うことができます。
お盆においても、ご先祖様の供養やお施餓鬼(※後述)などを行うことで、故人が来世でも幸せでいられるようにと願います。
なお、浄土真宗では「供養」という概念がない為、お盆でも供養は行わず、ご先祖様への感謝を捧げる行事と位置づけています。
► 家に戻ってくるご先祖様に感謝をするものとしてのお盆
日本古来の祖霊信仰では、ご先祖様は神となって子孫を見守るものとされています。また、神社の例祭にみられるように、神を迎えて歓待することで感謝を示し、引き続きの加護を願って送り出す風習があります。
お盆でご先祖様を迎えて食事でもてなすのも、同様の意味を持つと考えられます。
お盆の由来
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、中国で成立したお経『盂蘭盆経(うらぼんきょう)』に書かれている話が起源であるとするのが通説です。
・・・
お釈迦様の弟子・目連(もくれん)は、安居(※)中に得意な神通力で亡き母の姿を見通したところ、母が餓鬼道に堕ち、飢えて苦しんでいるのがみえました。
目連は母に食べてもらおうと、神通力で食べ物を送りましたが、母が食べようとするとどれも燃えてしまい、口にすることができません。
お釈迦様に母を救う方法を尋ねたところ、
「あなたの母親は、生前に強欲に過ごしていた為に深い業を負い、餓鬼道に落ちた。7月15日に安居を終える僧侶たちに飲食物を捧げて供養を行えば、父母だけではなく七世前の祖先まで救われるであろう」
と言われ、目連がその通りにすると、その功徳によって母は餓鬼の苦しみから救われました。
・・・
この話から、お盆には故人の供養や施餓鬼(飢えや渇きに苦しむ死者に食べ物を施すこと)を行うようになりました。
※安居(あんご)...4 月 16 日~7 月 15 日に行われるお坊さんの修行期間
今までの説は間違い!?「盂蘭盆」の新説
お盆の語源を説明する際、「盂蘭盆」はサンスクリット語の「ウランバナ(=倒懸・逆さ吊り)」を意味する、という説が多く聞かれます。しかし、実は『盂蘭盆経』の中には逆さ吊りに関する記述は出てきません。
そこに疑問を持った研究者が2013年に提唱した説が、
「サンスクリット語を口語形にした際に音が変化しており、本来の "盂蘭盆" とは "ご飯をのせた盆(器)" を意味する」
というものです。
実際、『盂蘭盆経』の中には「(僧侶たちに)盂蘭盆を捧げなさい」という記述があることから、今までの通説は誤りで、この説が正しいのかもしれません(真相は昔の人しか知りませんが...)。
お盆には何をする?
「お盆=お墓参りの時期」という認識は多くの方が持っているように思いますが、本来はお墓参りだけではなく、各家庭にご先祖様(精霊)をお迎えし、もてなす行事です。
通常、「お盆の期間」と言えば7月ないし8月の13日~16日の4日間のみを指しますが、実際はそれに先駆けて準備が進められます。
近年は仏壇のない家も増えたことから、各家庭にお迎えする風習も徐々に廃れつつあるかもしれません。
ここでは、精霊迎えの為に用意するものや流れについて簡単に解説します。
ただし、細かい内容は地域やお寺(宗派)によって大きく異なるようです。実際に精霊迎えをしたいと思われたら、事前にお世話になっているお寺に確認しておくのがよいでしょう。
月初め~13日
月の始め頃から準備を始め、お盆期間の初日にあたる13日の「盆の入り」を迎えます。
盆棚作りや仏具磨き、墓掃除、盆提灯を灯し始めたりもします。
7月7日(8月盆であれば8月7日)を盆行事の初めの日とする地域もあり、七日盆(ナヌカボン)やナヌカビと呼ばれます。
► 盆棚(ぼんだな)
お盆の期間中に設けられる棚で、精霊棚(しょうりょうだな)ともいわれます。
細かいしつらえは地域や宗派ごとに異なりますが、仏壇の前に菰(こも)を敷いた机を設け、位牌や、精霊馬などを飾るのが一般的です。
また、お盆中は盆棚にご先祖様用のお食事や、施餓鬼の為の水などを供えます。
13日までに飾り付けを終え、17日には片付けることが多いようです。

► 盆提灯(ぼんちょうちん)
盆棚の傍に据えられ、お盆の期間中、あるいは8月初~8月末の間(新盆の地域では7月初~7月末)灯しておきます。
ご先祖様に迷わず帰って来てもらうための目印になります。
▶ 精霊馬(しょうりょううま)
ご先祖様が浄土から行き来する際に使用する乗り物に見立てており、お盆の期間中、盆棚や玄関に置かれます。
浄土からこちらに帰ってくる際は早く帰ってきてもらうためにキュウリの馬を、帰りはゆっくり帰って欲しいという気持ちを込めてナスの牛を使用してもらう、といわれています。
13日の夕方(迎え盆・盆入り)
夕方に家の門口や玄関で迎え火を焚きます。精霊(亡くなった方の魂)は迎え火を目印に家に戻ってきます。
あるいは、墓前で火を焚き、その火を手持ち提灯に移して家までご先祖様をご案内する風習もあるようです。
また、京都では迎え火ではなくお寺で「迎え鐘」をつく方が馴染みがああったりと、やはり地域によって違いがあります。
► 迎え火(むかえび)
かわらけ(素焼きの皿)の上で、麻殻(おがら)などを燃やします。門口や玄関で迎え火を焚き目印にすることで、ご先祖様が迷わず帰って来られるようにします。

14日・15日 (盆中日)
朝昼晩の食事を供えてご先祖様と過ごします。
この間に僧侶にお経を上げていただいたり(棚経)、お墓参りをします。

16日(送り盆・盆明け)
お盆期間の最終日です。朝昼は前日と同様に食事をお供えし、夕方に家の門口や玄関で送り火を焚いて精霊を送り出します。
► 送り火(おくりび)
迎え火と同じく、家の前で火を焚きご先祖様を見送ります。
この時に、解体した精霊馬やお供え物などを菰(こも)に包んだものを送り火にくべて、お土産として精霊に持ち帰っていただくという風習もあります。
17日~月末
盆棚や盆提灯の片付けをします。
お盆に行う法要
仏教行事でもあるお盆には、僧侶にお経をあげていただくのも慣例です。
寺院に檀信徒が集まって合同法要を行ったり、自宅で個別にお経をあげていただきます。

棚経(たなぎょう)
ご先祖様をお迎えした盆棚の前で、僧侶にお経をあげていただくことを棚経といいます。
本来は迎え火~送り火の間にしていただくものですが、数日の間に檀信徒の全戸を回るのは難しい為、お盆までの半月~1ヶ月をかけて各家を回ることが多いようです。
迎え火前に棚経をする際は、盆棚ではなく普段の仏壇の前で読経をしていただけます。
お施餓鬼(せがき)
施餓鬼会(せがきえ)ともいいます。
死後に餓鬼道(がきどう)に落ちて餓鬼になった人へ食べ物や飲み物などを施し、供養するものです。
お施餓鬼自体は行う時期に決まりはありませんが、先述の『盂蘭盆経』の話に因み、お盆にお寺でお施餓鬼を行うことがあります。
初盆(はつぼん)
故人が亡くなり四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆のことで、盆棚を特別な設えにして手厚く迎えるほか、僧侶に初盆法要をお願いすることもあります。
四十九日より前にお盆を迎えた場合は、故人の魂がまだこちらの世界に留まっている期間となる為、翌年のお盆が新盆となります。
初盆を新盆(にいぼん・しんぼん)と呼ぶこともありますが、旧暦のお盆と新暦のお盆を呼び分ける際の「新盆」と呼称が同じなので、混同しないように注意が必要です。
※お盆前のお寺は大変忙しくされています。棚経や初盆、その他法要を依頼する際には、早めのご相談をおすすめします。
お盆に関連した行事
今やなかば観光イベント化したものや、お祭りのように思われている行事も、本来はお盆に因んだ行事のものもあります。
五山の送り火
京都の夏の風物詩の一つ、8月16日にご先祖様をあの世に送り出す為の行事です。
京都市街を囲む山の中腹に「大」「妙法」「舟形」「左大文字」「鳥居」の5つの文字や絵を灯で描きます。江戸時代には倍の十山あったとか。
観光的要素も強くなった行事ではありますが、あくまでもご先祖様を見送る為のお盆の「送り火」。うかつに「大文字焼き」と言うと、京都民に「ちゃいまっせ」と訂正される、という逸話もありますが、今もお盆の行事の一つとして捉える意識が高いことの表れなのです。

灯籠流し
死者の魂を弔うために灯篭を川や海に流す行事で、主にお盆の送り火の一種として各地で行われている他、第二次世界大戦の戦没者の慰霊目的で行う地域もあります。
起源は中国ともいわれていますが、死者の世界が山の向こうや海の彼方にあると考える日本古来の考え方とも合致して定着したとも考えられます。
環境汚染への配慮で、近年は流した灯籠を下流で回収することもあるとか。ご先祖様はそのまま流れに乗って無事に海の向こうに辿り着けていると信じましょう...

精霊流し
灯篭流しと同じく、お盆に帰ってきたご先祖様を極楽浄土へ送るための行事です。
長崎県で行われるものが有名で、大きく派手な精霊船に供物を載せ、初盆を迎えた故人の遺族が担いで町内を練歩き、海へ流します。
やはり中国由来の「彩舟流し」が元となったといわれており、町内を練り歩く際に爆竹をならすのも中国の文化の名残だそう。
なお、長崎ほど賑やかではありませんが、小さな精霊船に供物をのせて海に流す地域もあります。
盆踊り
故人を供養する為の行事で、寺社の境内や公園で地域住民が集まって行うのが一般的ですが、初盆を迎える遺族の家に赴いて行う風習もあるそうです。
持空也上人の踊り念仏が各地の民族風習と結びついて広まったという説が有力ですが、「地獄での責苦を免れた亡者たちが、喜んで踊る状態を模した」「地踏みによる悪霊鎮魂の呪的意味合いがある」など、様々ないわれがあります。
徳島県の阿波踊りや沖縄のエイサーも盆踊りの一種です。
各地の盆踊りが「風流踊(ふりゅうおどり)」としてユネスコ無形文化遺産に登録される一方で、近年は近隣の騒音対策としてイヤホンを使用した新しい形式の「サイレント盆踊り」もあるとか。
まとめ
社会の変化とともに、お盆の精霊迎えを実際に見たり体験したことのある人は徐々に減り、馴染みのないものになりつつあるかもしれません。
慣例としての作法やマナーはありますが、旧来通りのことができなくても、ご先祖様へ想いを馳せて供養と感謝の気持ちを持つことが大切です。お墓参りや、お寺の合同法要の参加だけでもしてみてはいかがでしょうか。
筆者は幼少期に親の帰省に連れて行かれ、盆棚や迎え火をした記憶があります。夏の思い出とお盆は密接に紐づいており、お盆の期間になると家族や親族と過ごした楽しい記憶だけでなく、しみじみとご先祖様を思う気持ちが喚起されもします(年をとったせいもあるかもしれませんが...)。
日本ならではの夏の過ごし方やご先祖様を想う風習、この風情が、少しでも長く受け継がれて欲しいな、と思います。