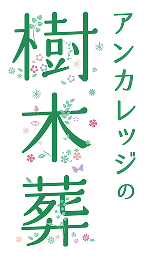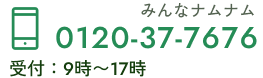静かに、緑の中で眠るという選択。
世界的庭園デザイナー石原和幸氏とつくる樹木葬は、あなたに寄り添い、
”これからもつながっていく場”を目指しています。
庭園設計の考え方、花や緑
そしてアンカレッジと共創する樹木葬への想いをお伺いしました。
原風景に宿る、庭づくりの原点

石原先生にとっての庭づくりやお花に対する想いをお聞かせください。
花と緑を通じて、地域の在り方をより豊かにしたい。
私の庭づくりの原点であり、今も変わらぬ願いです。
私は、長崎の爆心地から3kmほどの場所に戦後しばらく経ってから生まれました。そこは谷あいの町で、周囲には棚田が広がり、自然に囲まれた環境でした。6月には蛍が谷を舞い、8月になると赤とんぼが西日に照らされて一面がキラキラと輝く。そのような景色が、私にとっての日常でした。800人ほどの小さな町でしたが、たくさんミカンがなったら、皆で分かち合い、まるで一つの家族のように助け合いながら暮らしていて、豊かな自然と食べ物があれば、人は優しくなれるんだという実感がありました。この原体験が、今の私の庭づくりの根底にあります。 災害や戦争など、世界中でいろいろな出来事が起こっていますが、花や緑があるだけで、人は笑顔になれる。私はそう信じていて、生涯をかけて庭づくりに取り組んでいきたいと考えています。
 三原庭園
三原庭園
実際の庭づくりにおいてどのようなことを意識されていますか?
椿や桜が咲けばメジロが蜜を吸いに訪れ、樹木に集まる虫をシジュウカラが食べに来る。小鳥や蝶がやってきて、庭が小さな生態系になる。私は「街に庭がある」のではなく「庭の中に街がある」という考え方で庭づくりを行っています。そうした想いを実践する場所として、私は地元長崎に「三原庭園」をつくりました。約4年前から本格的に整備を始め、今では年間10万人以上が訪れる場所になり、ありがたいことに高い評価をいただいています。カフェやバーも併設し、誰でも気軽に訪れられる庭園です。私は、建築の最高峰がバルセロナのサグラダ・ファミリアだとすれば、庭の最高峰は三原庭園になるように、いずれは地域に引き継いでいける「人が集い、笑顔になれる場所」を目指しています。
命の循環を感じる、
アンカレッジの樹木葬に託す想い
アンカレッジの樹木葬の庭園デザインのコンセプトなどお聞かせください。
「自分がここにいるのはなぜか?」その問いの答えは、家族やご先祖の存在だと思っています。両親がいて、祖父母がいて、その先のご先祖がいる。だからこそ、迷ったときや節目のときに、人はお墓参りに行くのだと思います。ご先祖に会える、語りかけることができると感じられるような樹木葬を、私はつくりたいですね。
ただ花や緑を植えるのではなく、その場所の生態系ごとデザインする。それが私の樹木葬づくりです。たとえば桜や椿など花の咲く木を植えれば、季節ごとに鳥がやってくる。マリーゴールドやブルーサルビアといった草花は蝶を呼び、小鳥や蝶が訪れる樹木葬は、「この蝶、おじいちゃんかな」と感じられるような、命のつながりを感じさせてくれる空間になると思うんです。
お墓という場所が、公園のように緑豊かな空間になると良いですね。お寺の敷地内にある山や斜面も活かしながら、鳥や蝶が山から下りてきてまた戻っていくような風景をつくっていきたい。つまり、地域の花や緑が増えることで生態系も豊かになっていく。そうした視点で花や樹の選定をしています。
地域に根ざし、
未来へつなぐ祈りの場所

樹木葬におけるデザインの力をどのように感じていらっしゃいますか?
特別な用地を新たに確保するのではなく、今ある敷地をどう活かしていくか。そこにこそ、私たちのデザインの力が発揮できると思っています。敷地内に花や緑が増えることで、そのお寺にご縁のある方だけでなく、地域の人たちもお寺に訪れるようになったり、今まで中々お墓参りに来なかった方が、お墓に立ち寄ってベンチからお花を眺める。そのような風景が生まれてきたらいいなと思います。
そうした「賑わい」が生まれることで、お寺やその周辺が、より多くの人にとって親しみやすく、心の拠り所のような存在になっていく。日常のなかに自然とご先祖、また、仏さまとのつながりを感じられる場所があることは、これからの時代においても大切なことだと思います。
故郷を離れて暮らす方でも、自宅の近くにお墓があることで、思い立ったときに立ち寄ることができます。そうして自然とお参りを重ねることが、ご本人にとっても、子どもやお孫さんにとっても、ご先祖を大切に思う心を育てる、豊かな時間になっていくのではないでしょうか。
「庭の中にお寺がある」
-新しい景色を描く-
アンカレッジと作る樹木葬について、今後の展望をお聞かせください。
今後も、アンカレッジさんと一緒に、一年一年進化させていけたらと思っています。私の理想にはなりますが、お墓を訪れたときに川や滝があり、本当にお花見ができるような自然豊かな場所になったら素敵ですよね。そうした自然のなかに樹木葬を配置していくことで、お寺そのものの価値も高まっていく。「庭の中にお寺がある」ようなイメージですね。お寺にはもともと歴史や物語があるわけで、そこに私たちの樹木葬が加わることで、新しい価値が生まれ、地域にこの価値が共有され、それがお寺の歴史の一部として積み重なっていけば良いなと思います。
そして、お寺が地域にとって「なくてはならない存在」になる未来を、一緒につくっていけたらと願っています。花や樹木だけでなく、水のある風景を採り入れたり、お寺でガーデンセミナーを開いたりするのも良いですね。お寺に馴染みのなかった方でも、花や緑を通じて関心を持ち、そこから地域全体にその魅力が広がっていく。そんなふうに、樹木葬のあるお寺が地域に花や緑を増やす拠点になっていけたら、とても嬉しいです。
 チャールズ国王と
チャールズ国王と ガレージガーデン
ガレージガーデン 故エリザベス女王と
故エリザベス女王と 羽田空港
羽田空港

株式会社石原和幸デザイン研究所
代表取締役 石原 和幸
1958年 長崎県生まれ
ランドスケープデザイナー・造園家
22歳で生け花の根源『池坊』に入門。苔を使った庭で独自の世界観が国際ガーデニングショーの最高峰「英国チェルシーフラワーショー」で高く評価され、多くの金賞を受賞。故エリザベス女王から“緑の魔術師”と称される。緑化プロデューサーとして日本各地で緑を使った街づくりを実施し、これまで全国各地で「みどりの大使」も務め、講演会やセミナー(花教室)の講師としても活動。2018年北京万博招聘デザイナー